今日は成人の日ですね。
昨年4月に30歳を迎えた私は、成人式(2013年)からちょうど10年になります。あれからもう10年も経つのか・・・。「三十路式」じゃないですけど、30歳ということで同窓会みたいなものは特に行われないようです。私に連絡が来てないだけかもしれませんが。
ところで今年の成人の日は、2022年4月1日の改正民法の施行により成人年齢が20歳から18歳に引き下げられてから初めての成人の日です。各地の「成人式」がどうなるか気になっていましたが、ほとんどの自治体では「二十歳の集い」などと名称を変更してこれまで通り20歳を対象とした記念行事を継続するそうです。
成人式を何歳で行うか、NHKが全国47の都道府県に問い合わせたところ、18歳の新成人を対象とするのは3つの市と町にとどまり、ほとんどの自治体が20歳のままであることがわかりました。
“18歳成人”初の成人の日 成人式の対象はほとんどが20歳 – NHK
成人の日に本当の「新成人」(18歳)ではなく20歳の人たちが集まるというのはへんてこりんですが、まあ、わざわざ式典をするのなら20歳のほうがいいでしょうし、私も若者であれば20歳での開催を望んでいたでしょう。
18歳といえばまだ高校3年生。高校生なんてまだまだ親と学校の庇護下にあるわけで、ほとんどの人は地元にいます。「18歳成人式」ならわざわざ自治体が主体となって式典なんてやる必要はなく、各高校でこじんまりとした式典をすればそれで十分だと思います。1月シーズンは受験や新生活準備があってバタバタしているという指摘もその通りです。
20歳という、高校を卒業してから2年ほど経ち、就職や進学をしてより自立した生活を送るようになり、地元を離れる人も多くなった時期にやるから「新成人」「成人式」としての特別感があり、同窓会としても上手く機能していました。自立もしていない高校3年生の18歳で成人式なんてやったところで何のありがたみもないでしょう。
そもそも、成人年齢の引き下げ自体が必要だったのか?ということからして疑問です。社会のあり方に関わる大きな変更なのに、いつのまにか決まっていた感があります。
就職・進学で親元を離れて自立した生活を送るときに、親の同意無しに契約等ができるようになったり便利なこともある一方で、最初の2年ぐらいは親の庇護下にあったほうが良いという感じもします。また、成人年齢は18歳だけど飲酒・喫煙・公営ギャンブル解禁は20歳から、国民年金加入も20歳から、犯罪も「特定少年」としてある程度少年法が適用されるところは、なんともちぐはぐです。もはや「成人」「未成年」という概念がぐちゃぐちゃになっている印象です。
Q1 どうして民法の成年年齢を18歳に引き下げるのですか?
A 我が国における成年年齢は,明治9年以来,20歳とされています。
近年,憲法改正国民投票の投票権年齢や,公職選挙法の選挙権年齢などが18歳と定められ,国政上の重要な事項の判断に関して,18歳,19歳の方を大人として扱うという政策が進められてきました。こうした政策を踏まえ,市民生活に関する基本法である民法においても,18歳以上の人を大人として取り扱うのが適当ではないかという議論がされるようになりました。世界的にも,成年年齢を18歳とするのが主流です。 成年年齢を18歳に引き下げることは,18歳,19歳の若者の自己決定権を尊重するものであり,その積極的な社会参加を促すことになると考えられます。
民法(成年年齢関係)改正 Q&A – 法務省
なぜ成人年齢を引き下げるのか?という国からの答えは「投票権・選挙権が18歳になったから」で、なんの答えにもなっていません。議論の出発点が「成人年齢を18歳に引き下げるべきだ」ではなく、「選挙権が18歳になったから合わせるべき」というのはあまりにもお粗末で、18歳選挙権はマッチポンプ的な立法といえます。
成人年齢引き下げの端緒となった18歳選挙権は、憲法改正の国民投票法がそもそもの始まりです。
憲法改正を目指す第1次安倍政権下で2007年に成立した国民投票法は、18歳以上の国民に投票権を認めました。そして、附則にて
附則第3条 国は、この法律の施行後速やかに、年齢満18年以上満20年未満の者が国政選挙に参加することができること等となるよう、国民投票の投票権を有する者の年齢と選挙権を有する者の年齢との均衡等を勘案し、公職選挙法、民法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
日本国憲法の改正手続に関する法律 抄(平成19年法律第51号) – e-Gov
と定め、これが今日の18歳選挙権、18歳成人へと繋がることになります。
そもそも、成人年齢や選挙権が20歳のままで、急に憲法改正の投票権だけ18歳としたこと自体がおかしかったんですよね。まして附則で選挙権や成人年齢の引き下げにも言及しているのに、ろくに成人年齢引き下げの議論はせずにまず投票権だけ18歳としたわけです。こうなれば後の成人年齢の議論も当然引き上げありきとなり、話にならなくなります。
成人(選挙権)年齢の引き下げは、高齢者中心の「シルバー民主主義」を少しでも是正できるという好意的な意見もありますが、「年金を払わせるため」という穿った見方もありました。確かに、超高齢社会のカモフラージュや年金制度の延命としての成人定義や年金の担い手拡大は政権としても利がありそうです(なお先述の通り国民年金の加入は今も20歳から)。
しかし、とはいえ保守政党である自民党がいきなり成人年齢の引き下げを唱えるというのは長年謎に思っていました。今回、成人年齢引き下げについて色々調べていたのですが、どうやらこの国民投票の18歳投票権は、野党・民主党の主張だったようです。
当初、自民・公明両党と当時の民主党が提出したそれぞれの法案では投票権年齢に違いがあった。
前者は「20歳以上」、後者は「原則18歳以上、場合によっては16歳以上」だった。
協議の結果、自民・公明両党が民主党案を受け入れる形で、投票権の「18歳以上」が決まった。
(中略)
一方、18歳案を訴えた枝野氏は、憲法改正という大テーマにあたってはできるだけ多くの国民が参加すべきだと主張したと語る。
「憲法は長く使うものでしょ。日本は硬性憲法(=制度上、改正が容易ではない憲法)だから、1回変えることがあったとしても3年後にまたやりますという世界ではない。それは幅広でいいんじゃないのという理屈を何度も説明した。これだけはやりましょうよ、18歳でと」
なぜ、18歳から成人?~大人の線引きはなぜ決まった~ – NHK政治マガジン
2004年、自・公両党が、憲法改正国民投票法案の概要を固め、有権者を「20歳以上」としました。一方、民主党案は投票資格を「18歳以上」として対立しました。
2006年、法案を成立させたい自民党が民主党に譲って、投票年齢を「原則18歳以上」とすることが基本合意されました。
第2回 強い「追い風」は、国民投票法成立~改憲論議から始まった18歳選挙権 ―18歳への選挙年齢引き下げは「タナボタ」的に決まった ~それでも、若い人の政治への「気づき」の原点になるだろう – みらいぶプラス/河合塾
憲法改正という重大な問題はより多くの国民が参加して決めるべきというのは確かにその通りだと思いますが、まず投票権だけ18歳としたのはやっぱり議論の順番が逆だと思いますね。投票権だけ18歳と先に決めて、後から選挙権や成人年齢を議論しろというのはちょっと乱暴です。
憲法改正が宿願であった安倍政権下で憲法改正への一歩としてまず成立した国民投票法、少しでも憲法改正を前進させたいがゆえに民主党に譲歩せざるをえない面もあったのでしょう。
まあ、グローバルスタンダードも18歳成人ということもあり、もう18歳成人が元に戻ることはないのでしょうが、しばらくは違和感が続きそうです。成人の日の「二十歳の集い」は、18歳成人が定着してもそのままなんでしょうかねぇ。「昔の名残り」としての風物詩になっていくんでしょうか。。

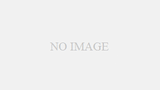

コメント